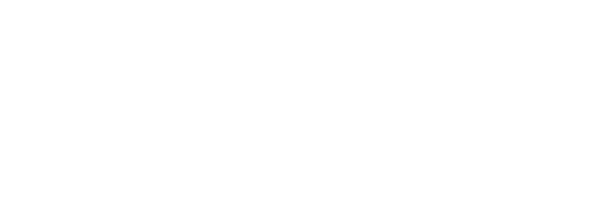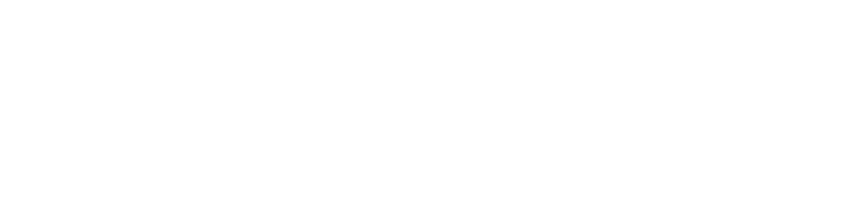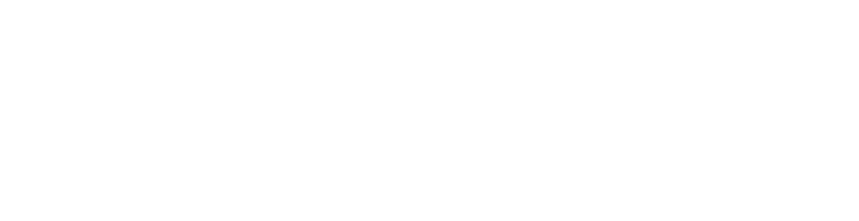大阪歌舞伎座[千日前] 1956年03月
-
昼の部1
-
昼の部2
-
昼の部3
-
昼の部4
-
夜の部1
-
夜の部2
-
夜の部3
-
夜の部4
- 場名など
- 足利家奥殿〜同床下〜問註所対決〜同控所刃傷
- 配役
-
仁木弾正 = 市川猿之助(2代目)
荒獅子男之助 = 實川延二郎(2代目)
栄御前 = 尾上菊次郎(4代目)
弾正妹八汐 = 坂東簑助(6代目)
右京妻沖ノ井 = 中村成太郎(2代目)
主水妻松嶋 = 上村吉弥(5代目)
茶道珍斎 = 片岡孝夫
腰元 = 獅道
腰元 = 嵐雛治
腰元 = 扇駒
腰元 = 中村章
腰元 = 國之丞
腰元 = 實川延枝
腰元 = 訥紀彌
腰元 = 良之助
申次の腰元 = 片岡松之丞(初代)
政岡一子千松 = 市川右之助(3代目)
足利鶴千代 = 中村栄治郎
乳人政岡 = 中村富十郎(4代目)
細川勝元 = 市川寿海(3代目)
山名宗全 = 嵐吉三郎(7代目)
渡辺外記左衛門 = 坂東簑助(6代目)
渡辺民部 = 市川団子(3代目)
山中鹿之助 = 嵐みんし(6代目)
笹野才藏 = 市川猿三郎(初代)
黒沢官藏 = 市川市十郎(5代目)
大江鬼貫 = 市川荒次郎(2代目)
下侍右源太 = 中村政之助(2代目)
下侍左源太 = 澤村宇十郎(4代目)
諸所の諸士 = 坂東吉弥(2代目)
諸所の諸士 = 紫香
諸所の諸士 = 市川升太郎(2代目)
諸所の諸士 = 片岡半蔵(3代目)
諸所の諸士 = 中村駒雀(初代)
諸所の諸士 = 實川延正
諸所の諸士 = 豊若
諸所の諸士 = 中村鴈右衛門
諸所の諸士 = 大ぜい
小姓 = 片岡銀杏
- 備考
- 東西合同大歌舞伎、十三代目片岡我童・二代目片岡秀太郎襲名披露、
- 場名など
- 配役
-
口上 = 林又一郎(2代目)
口上 = 市川荒次郎(2代目)
口上 = 市川団子(3代目)
口上 = 市川猿之助(2代目)
口上 = 片岡我童(13代目)
口上 = 片岡仁左衛門(13代目)
口上 = 片岡秀太郎(2代目)
口上 = 片岡孝夫
口上 = 嵐吉三郎(7代目)
- 備考
- 東西合同大歌舞伎、十三代目片岡我童・二代目片岡秀太郎襲名披露
- 場名など
- 天衣紛上野初花、松江邸広間〜同白書院〜同玄関先
- 配役
-
使僧北谷道海実は河内山宗俊 = 市川寿海(3代目)
家老高木小左衛門 = 坂東簑助(6代目)
松江出雲守 = 片岡仁左衛門(13代目)
重臣北村大膳 = 市川荒次郎(2代目)
近習頭宮崎数馬 = 實川延二郎(2代目)
近習大橋伊蔵 = 市川松柏(初代)
近習黒沢要人 = 坂東三津三郎(初代)
近習杉浦伴吾 = 紫香
近習米村丹蔵 = 中村政之助(2代目)
近習山野周介 = 市川升太郎(2代目)
近習間宮帯刀 = 片岡半蔵(3代目)
近習川口運平 = 實川延正
近習山岡林蔵 = 澤村宇十郎(4代目)
申次の近習 = 坂東吉弥(2代目)
仲間 = 海二郎
若党 = 坂東喜代志
小姓 = 中村鴈好
小姓 = 片岡銀杏
腰元浪路 = 片岡秀太郎(2代目)
腰元 = 市川春猿(初代)
腰元 = 中村駒雀(初代)
腰元 = 中村鴈之丞
腰元 = 片岡松之丞(初代)
腰元 = 大谷明代
腰元 = 坂東玉之助(4代目)
- 備考
- 東西合同大歌舞伎、十三代目片岡我童・二代目片岡秀太郎襲名披露、河竹黙阿彌作
- 場名など
- 配役
-
山蔭右京 = 坂東簑助(6代目)
奥方玉ノ井 = 中村富十郎(4代目)
太郎冠者 = 實川延二郎(2代目)
侍女千枝 = 市川猿三郎(初代)
侍女小枝 = 實川延太郎(4代目)
- 備考
- 東西合同大歌舞伎、十三代目片岡我童・二代目片岡秀太郎襲名披露
- 場名など
- 渡守頓兵衛住居
- 配役
-
渡守頓兵衛・新田義峰 = 片岡仁左衛門(13代目)
船頭六蔵 = 實川延二郎(2代目)
傾城うてな = 嵐雛助(10代目)
娘お舟 = 片岡我童(13代目)
- 備考
- 東西合同大歌舞伎、十三代目片岡我童・二代目片岡秀太郎襲名披露、内藤幸政作、岡倉士朗・巌谷真一共同演出
- 場名など
- 三輪大祝の住居〜蘇我入鹿の宮殿〜入鹿宮殿の裏庭〜生駒山の山砦〜地下の石牢〜大仏殿の内部
- 配役
-
三輪の氏人若い者 = 中村霞仙(2代目)
三輪の氏人若い者 = 嵐璃珏(5代目)
三輪の氏人若い者 = 市川松柏(初代)
三輪の氏人若い者・舞楽の男 = 坂東吉弥(2代目)
三輪の氏人若い者 = 紫香
三輪の氏人若い者 = 中村政之助(2代目)
三輪の氏人老人 = 中村福笑
三輪の氏人老人 = 嵐若橘
三輪の氏人老人 = 中村福二郎
三輪の氏人老人 = 雛太郎
三輪の氏人老人 = 当二郎
三輪の氏人老女 = 實川延正
三輪の氏人老女 = 中村鴈右衛門
三輪の氏人若い女 = 市川春猿(初代)
三輪の氏人若い女 = 片岡松之丞(初代)
三輪の氏人若い女 = 大谷明代
蘇我の岩根(武将入鹿の甥) = 市川荒次郎(2代目)
三輪の大祝(三輪氏の氏上・三輪神社の祭司) = 嵐吉三郎(7代目)
三輪の狭手彦 = 市川猿之助(2代目)
狭手彦の母 = 尾上菊次郎(4代目)
熊・従卒 = 市川升太郎(2代目)
大祝の娘飛鳥 = 市川団子(3代目)
大祝家の若い侍女 = 中村栄子
大祝家の若い侍女 = 和島由紀
大祝家の若い侍女 = 任田順好
大祝家の若い侍女 = 榎本悠子
大祝家の若い侍女 = 森本富美子
大祝家の若い侍女 = 林喜久子
兵の小頭・舞楽の男 = 坂東三津三郎(初代)
兵の小頭 = 片岡半蔵(3代目)
兵の小頭 = 関本
兵の小頭・従卒 = 市川荒右衛門(2代目)
兵士 = 大ぜい
蘇我の入鹿 = 坂東簑助(6代目)
入鹿の娘輝姫 = 万代峰子
入鹿の侍女 = 良之助
入鹿の侍女 = 雛尾
陰陽師百済虫麻呂 = 實川延二郎(2代目)
従僧 = 大ぜい
牢番甲 = 市川升太郎(2代目)
牢番乙 = 片岡半蔵(3代目)
三輪の女 = 荒木雅子
三輪の女 = 桂美保
三輪の女 = 小谷智子
三輪の女 = 八坂幹子
楽士の侍女 = 片岡松燕(2代目)
楽士の侍女 = 松葉
楽士の侍女 = 富尾
楽士の侍女 = 訥久彌
巫女 = 森垣登美子
巫女 = 中村栄子
巫女 = 和島由紀
巫女 = 任田順子
巫女 = 榎本愁子
巫女 = 森本富美子
巫女 = 由良路子
舞楽の男 = 實川延太郎(4代目)
舞楽の男 = 紫香
文官 = 三堀俊治
文官 = 横田一郎
文官 = 石橋彪
文官 = 床捷人
武官 = 妹尾康男
武官 = 窪田幸士
武官 = 山下功
奴れい老人 = 山口幸生
奴れい老人 = 森秀人
奴若い男 = 西山嘉孝
奴若い男 = 谷口完
奴若い男 = 安達国晴
奴若い男 = 矢荻頼秀
奴若い男 = 高田次郎
奴若い男 = 小河欣二
輿かく男 = 實川延枝
輿かく男 = 当升
輿かく男 = 当吉郎
輿かく男 = 成司
蘇我の武熊 = 市川猿三郎(初代)
蘇我の広国 = 中村松若(初代)
- 備考
- 東西合同大歌舞伎、十三代目片岡我童・二代目片岡秀太郎襲名披露、菊池寛作、大森痴雪脚色、久保田万太郎演出
- 場名など
- 四条宗清の広間〜同離座敷〜都万太夫座の楽屋
- 配役
-
坂田藤十郎 = 市川寿海(3代目)
宗清のお梶 = 中村富十郎(4代目)
都万太夫座座元万太夫 = 片岡仁左衛門(13代目)
霧浪千壽 = 片岡我童(13代目)
赤松梅龍に扮する役者 = 中村松若(初代)
大経師以春に扮する役者 = 市川猿三郎(初代)
道順に扮する役者 = 市川市十郎(5代目)
助右衛門に扮する役者 = 坂東三津三郎(初代)
助作に扮する役者 = 中村政之助(2代目)
万歳に扮する役者 = 豊若
道順妻に扮する役者 = 中村鴈右衛門
お玉に扮する役者 = 嵐みんし(6代目)
頭取 = 市川松柏(初代)
藤十郎の金剛 = 中村駒雀(初代)
藤十郎の弟子 = 海一郎
千壽の金剛 = 片岡松燕(2代目)
狂言方 = 實川延正
道具方 = 紫香
道具方 = 笹二郎
道具方 = 海二郎
道具方 = 秀六
道具方 = 松彌
囃子方 = 訥紀彌
囃子方 = 吉一
囃子方 = 實川みのる
囃子方 = 良之助
丹波屋主人 = 中村霞仙(2代目)
丹波屋丁稚 = 中村鴈好
八幡屋手代 = 坂東吉弥(2代目)
幇間久古 = 嵐璃珏(5代目)
遊女 = 上村吉弥(5代目)
遊女 = 坂東玉之助(4代目)
遊女 = 中村鴈之丞
色子 = 路子
色子 = 由紀
色子 = 順好
色子 = 恵子
色子 = 栄子
色子 = 富美江
色子 = 登美子
色子 = 悠子
色子 = 美保
色子 = 喜久子
仲居 = 國之丞
仲居 = 富尾
仲居 = 扇駒
- 備考
- 東西合同大歌舞伎、十三代目片岡我童・二代目片岡秀太郎襲名披露、岡村柿紅作