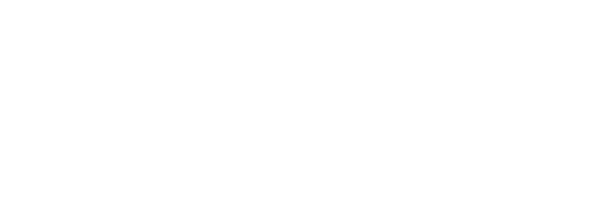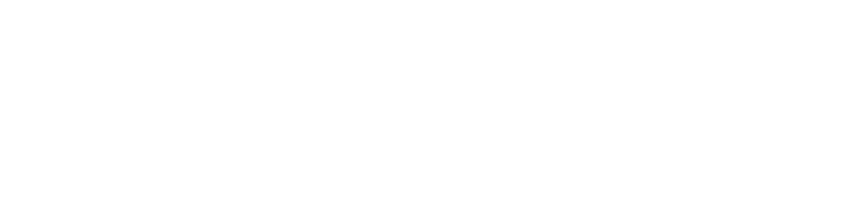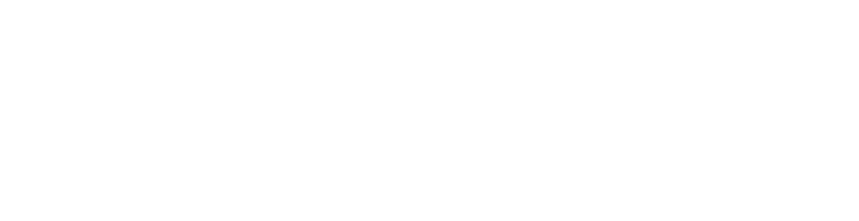大阪歌舞伎座[千日前] 1951年11月
-
昼の部1
-
夜の部1の1
-
夜の部1の2
-
夜の部1の3
-
夜の部1の4
-
夜の部1の5
- 場名など
- 桐壺の巻上〜桐壺の巻下〜夕顔の巻〜若紫の巻〜紅葉賀の巻〜賢木の巻〜須磨明石の巻
- 配役
-
光君 = 市川寿海(3代目)
頭中將・三位中將 = 片岡仁左衛門(13代目)
桐壺の御門・桐壺の御門の靈 = 阪東寿三郎(3代目)
桐壺の更衣・四の宮(後の藤壺の更衣)・藤壺の女御 = 中村富十郎(4代目)
橘典侍 = 中村鴈治郎(2代目)
海龍王 = 坂東簑助(6代目)
兵部卿の宮 = 實川延二郎(2代目)
弘徽殿の女御 = 嵐雛助(10代目)
六條御息所の生靈 = 尾上菊次郎(4代目)
夕顔 = 坂東鶴之助(4代目)
左大臣 = 林又一郎(2代目)
左中辨 = 市川九團次(3代目)
大藏卿の藏人・右近將監藏人 = 嵐璃珏(5代目)
光君の乳母大貳の子惟光・民部大輔惟光 = 嵐吉三郎(7代目)
惟光兄阿闍梨・山の座主 = 中村霞仙(2代目)
惟光妹婿三河守・家司良清朝臣 = 中村松若(初代)
院の預り豊後介 = 浅尾奥山(8代目)
豊後介の子瀧口の武士・藤壺の中宮の叔父横川僧都 = 市川寿美蔵(7代目)
按察大納言の北の方桐壺更衣の母 = 市川新之助(5代目)
後涼殿の更衣 = 松本錦吾(2代目)
命婦の君 = 上村吉弥(5代目)
光君(若き頃) = 中村扇雀(2代目)
頭中將(若き頃)・侍女右近 = 市川雷蔵(8代目)
侍從 = 市川松柏(初代)
左中辨弟・上の女房 = 中村駒雀(初代)
上の女房 = 延之亟
上の女房 = 嵐冠十郎(6代目)
輦車の夫 = 松本松二郎
輦車の夫 = 當太郎
輦車の夫 = 當二郎
輦車の夫 = 榮
侍女桔梗 = 上村吉弥(5代目)
侍女刈萱 = 實川延太郎(4代目)
侍女このぶ = 中村鴈之丞
侍女 = 中村章
侍女 = 中村駒雀(初代)
侍女 = 孝一
殿上人 = 市川松柏(初代)
殿上人 = 紫香
殿上人 = 嵐若橘
殿上人 = 豊若
殿上人 = 中村福笑
殿上人 = 中村福二郎
上達部 = 中村政之助(2代目)
上達部 = 坂東三津三郎(初代)
上達部 = 澤村宗弥
上達部 = 坂東簑三郎
鷹匠 = 伊之助
舎人 = 當久治
舎人 = い千助
上の女房 = 延之亟
上の女房 = 中村駒雀(初代)
上の女房 = 嵐冠十郎(6代目)
上の女房 = 市川新二郎
上の女房 = 豊太郎
更衣 = 雛太郎
更衣 = 尾上笹太郎
更衣 = 笹之助
更衣 = 嵐雛治
御隨身 = 實川延正
御隨身 = 扇太郎
親王 = 尾上笹太郎
親王 = 嵐雛治
春宮 = 片岡彦人
某の女房 = 延之亟
女房 = 實川延枝
女房 = 關二郎
女房 = 市川新二郎
女房 = 豊太郎
光君の家來 = 實川延正
三位中將の從者 = 嵐冠十郎(6代目)
三位中將の從者 = 鴈太郎
牛飼の童子 = 桂代子
女の童・童子 = 小芳
- 備考
- 藝術祭参加 大阪市民文化祭参加 十一月大歌舞伎、舟橋聖一脚色、谷崎潤一郎監修、久保田万太郎演出、吉村忠夫美術考証、安田靱彦美術監督
- 場名など
- (通し)千代田城中大溜の間〜營中高家控えの間〜同大名衆着替えの間〜同奥溜りの間〜同松のお廊下〜同白書院
- 配役
-
脇坂淡路守 = 市川寿海(3代目)
淺野内匠頭 = 中村鴈治郎(2代目)
吉良上野介 = 澤村訥子(8代目)
伊達左京亮 = 尾上菊次郎(4代目)
畠山民部少輔 = 松本錦吾(2代目)
品川豊前守 = 市川寿美蔵(7代目)
大友近江守 = 中村松若(初代)
大澤左京太夫 = 上村吉弥(5代目)
淺野の家臣片岡源五右衞門 = 坂東簑助(6代目)
淺野の家臣武林唯七 = 嵐吉三郎(7代目)
淺野の家臣磯貝十郎左衛門 = 市川雷蔵(8代目)
松原佐中 = 嵐璃珏(5代目)
伊達左京亮の家來内山權太夫 = 中村政之助(2代目)
京極の家來高松與九郎 = 延之亟
岡部の家來藤澤五右衛門 = 坂東三津三郎(初代)
加納因幡守の家來増山四郎兵衛 = 澤村宇十郎(4代目)
梶川與三兵衛 = 浅尾奥山(8代目)
茶坊主關久和 = 紫香
大名 = 嵐冠十郎(6代目)
大名 = 坂東簑三郎
大名 = 實川延正
大名 = その他大ぜい
茶坊主 = 中村章
同 = 扇駒
諸大名の家來 = 大ぜい
- 備考
- 藝術祭参加 大阪市民文化祭参加 十一月大歌舞伎、通し狂言、瀨川如皐編・演出、松田種次装置、元禄事暦二百五十年記念上演
- 場名など
- (通し)田村右京太夫邸
- 配役
-
淺野内匠頭 = 中村鴈治郎(2代目)
家臣片岡源五右衞門 = 坂東簑助(6代目)
田村右京太夫 = 中村霞仙(2代目)
庄田下總守 = 林又一郎(2代目)
介錯人磯田武太夫 = 市川松柏(初代)
多聞傅八郎 = 市川九團次(3代目)
近習の侍 = 大勢
足軽 = 大勢
- 備考
- 藝術祭参加 大阪市民文化祭参加 十一月大歌舞伎、通し狂言、瀨川如皐編・演出、松田種次装置、元禄事暦二百五十年記念上演
- 場名など
- (通し)山科大石閑居
- 配役
-
大石内藏助 = 阪東寿三郎(3代目)
大石主税 = 坂東鶴之助(4代目)
下僕岡平實ハ高村逸平太 = 片岡仁左衛門(13代目)
醫者玄伯 = 嵐璃珏(5代目)
太鼓持夢助 = 中村政之助(2代目)
太鼓持勝作 = 澤村宇十郎(4代目)
太鼓持市八 = 坂東三津三郎(初代)
太鼓持 = 中村福笑
太鼓持 = 嵐若橘
太鼓持 = 豊若
駕籠屋 = 鴈太郎
駕籠屋 = 扇太郎
藝者小若 = 實川延太郎(4代目)
藝者笑香 = 中村鴈之丞
藝者 = 尾上笹太郎
藝者 = 嵐雛治
藝者 = 中村章
舞妓小蝶 = 小芳
舞妓 = 富右衞門
舞妓 = 智子
舞妓 = 鯉子
母千壽 = 市川新之助(5代目)
妻およし = 中村鴈治郎(2代目)
下女おさよ = 上村吉弥(5代目)
仲居おさく = 延之亟
仲居おしげ = 中村駒雀(初代)
仲居 = 雛太郎
仲居 = 笹之助
仲居 = 關二郎
仲居 = 扇駒
- 備考
- 藝術祭参加 大阪市民文化祭参加 十一月大歌舞伎、通し狂言、瀨川如皐編・演出、松田種次装置、元禄事暦二百五十年記念上演
- 場名など
- (通し)吉良邸牧山丈左衞門宅〜麹町堀端〜飯田町裏長屋〜吉良邸清水一角宅〜再び飯田町裏長屋〜九段牛ヶ淵堀端
- 配役
-
清水一角 = 阪東寿三郎(3代目)
一角姉おまき = 中村富十郎(4代目)
一角弟輿一郎 = 實川延二郎(2代目)
小山田庄左衞門 = 市川寿海(3代目)
腰元お市 = 延之亟
腰元お竹 = 中村鴈之丞
門弟岩淵平馬 = 市川九團次(3代目)
門弟米澤小五郎 = 市川寿美蔵(7代目)
門弟矢部十内・仲間權平 = 中村松若(初代)
門弟松倉新吾 = 市川松柏(初代)
牧山丈左衞門 = 澤村訥子(8代目)
小林の小僧子之助 = 片岡秀公
樽酒屋勘助 = 中村霞仙(2代目)
吉良家の仲間 = 嵐冠十郎(6代目)
通行の男 = 松本松二郎
通行の男 = 菊三郎
通行の丁稚 = 榮
通行の女 = 智子
通行の女 = 鯉子
樽酒屋女房おらく = 松本錦吾(2代目)
娘お雪 = 中村扇雀(2代目)
母おむつ = 市川新之助(5代目)
- 備考
- 藝術祭参加 大阪市民文化祭参加 十一月大歌舞伎、通し狂言、瀨川如皐編・演出、松田種次装置、元禄事暦二百五十年記念上演
- 場名など
- (通し)吉良邸奥庭泉水〜同炭小屋
- 配役
-
大石内藏助 = 阪東寿三郎(3代目)
大石主税 = 坂東鶴之助(4代目)
小林平八郎 = 片岡仁左衛門(13代目)
吉良上野之助 = 澤村訥子(8代目)
大高源吾 = 市川九團次(3代目)
間十次郎 = 嵐璃珏(5代目)
堀部彌兵衞 = 浅尾奥山(8代目)
不破數右衞門 = 市川寿美蔵(7代目)
汐田又之亟 = 上村吉弥(5代目)
間瀨孫九郎 = 市川松柏(初代)
大石瀨左衞門 = 實川延太郎(4代目)
磯貝十郎左衞門 = 市川雷蔵(8代目)
矢頭右衞門七 = 片岡秀公
近松勘六 = 紫香
富森助右衞門 = 中村政之助(2代目)
勝田新左衞門 = 澤村宇十郎(4代目)
茅野和助 = 中村駒雀(初代)
小野寺十内 = 延之亟
岡野金右衞門 = 中村鴈之丞
吉良の附人 = 坂東三津三郎(初代)
吉良の附人 = 嵐冠十郎(6代目)
吉良の附人 = 實川延正
そのほか = 大勢
- 備考
- 藝術祭参加 大阪市民文化祭参加 十一月大歌舞伎、通し狂言、瀨川如皐編・演出、松田種次装置、元禄事暦二百五十年記念上演