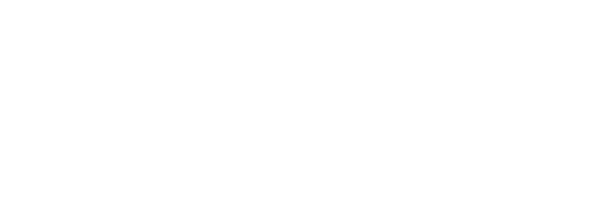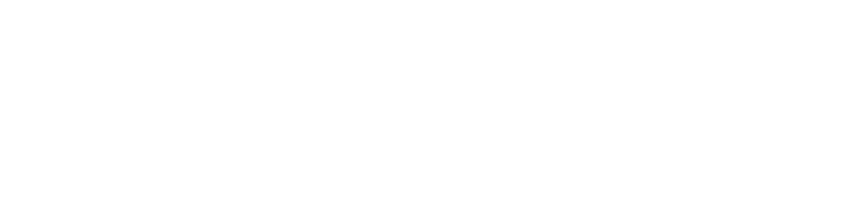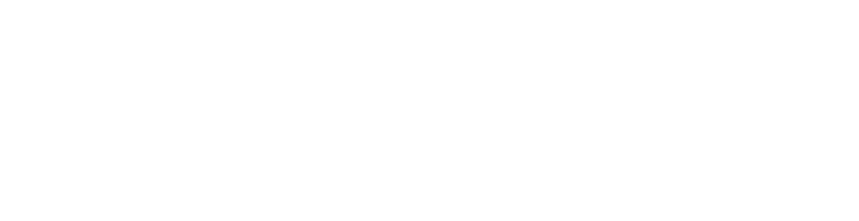中座 1953年10月
-
昼夜入替1
-
昼夜入替2
-
昼夜入替1
-
昼夜入替2
-
昼夜入替3
- 場名など
- (通し)平野村お三内〜紀州加太の浦〜美濃国常楽院〜大岡邸奥座敷〜同不浄門〜常盤橋御門外〜水戸家奥庭〜奉行役宅書院〜紀州幸伝寺前〜大岡邸奥座敷〜奉行役宅
- 配役
-
徳川天一坊実ハ感応院の弟子法沢・池田大助 = 坂東鶴之助(4代目)
大岡越前守 = 片岡仁左衛門(13代目)
大岡妻小沢 = 尾上菊次郎(4代目)
山内伊賀之亮・水戸綱條 = 澤村訥子(8代目)
庄屋甚右衛門 = 市川新之助(5代目)
藤井左京・久保見杢四郎 = 中村松若(初代)
上使土屋相模守 = 林又一郎(2代目)
山内妻小佐美 = 嵐雛助(10代目)
赤川大膳 = 嵐璃珏(5代目)
住職天忠・おさん = 浅尾奥山(8代目)
用人白石治右衛門 = 嵐吉三郎(7代目)
吉田三五郎 = 嵐三右衛門(10代目)
小姓山辺主悦・志目田丈助 = 片岡秀公
大岡一子忠右衛門 = 片岡彦人
感応院下男久助 = みんし2
百姓畑六・足軽運平 = 中村政之助(2代目)
百姓田吾作 = 松本豊
娘おしも = 實川延太郎(4代目)
所化天一・水戸家腰元 = 松之亟1
百姓久根八・供侍・近習 = 獅道
百姓麦三 = 菊三郎
百姓米八 = 澤村訥久蔵
花屋の娘お絹 = 嵐雛治
足軽権平・花屋の後家お民 = 澤村宇十郎(4代目)
水戸家腰元・近習 = 関二郎
大岡の小姓 = 悦子
供侍 = 当二郎
供侍 = 松本松二郎
供侍・近習 = 良之助
供侍・捕方 = 若橘3
若侍金吾・供侍 = い千助
供侍 = 吉太郎
捕方・近習 = 八重十郎
新造 = 尾上笹太郎
- 備考
- 錦秋を飾る唯一の東西大歌舞伎十月興行、4〜14日昼の部・15〜26日夜の部、河竹黙阿弥作、瀬川如皐改補並演出、大塚克三装置
- 場名など
- 新吉原揚屋
- 配役
-
傾城宮城野 = 尾上菊次郎(4代目)
妹信夫 = 嵐雛助(10代目)
大黒屋惣六 = 澤村訥子(8代目)
新造宮里 = 澤村宇十郎(4代目)
新造宮柴 = 若橘3
新造宮船 = 尾上笹太郎
禿たより = 悦子
遣手おまき = 関二郎
- 備考
- 錦秋を飾る唯一の東西大歌舞伎十月興行、4〜14日昼の部・15〜26日夜の部
- 場名など
- 川連法眼館
- 配役
-
佐藤四郎兵衛忠信実ハ源九郎狐 = 坂東鶴之助(4代目)
源義経 = 林又一郎(2代目)
静御前 = 尾上菊次郎(4代目)
亀井六郎 = 嵐璃珏(5代目)
片岡八郎 = みんし2
申次の侍 = 澤村宇十郎(4代目)
- 備考
- 錦秋を飾る唯一の東西大歌舞伎十月興行、4〜14日夜の部・15〜26日昼の部
- 場名など
- 備前岡山城下外れ笹ヶ淵池〜雀部善馬の家〜同夜
- 配役
-
雀部善馬 = 片岡仁左衛門(13代目)
雀部妻弓枝 = 尾上菊次郎(4代目)
若党万助 = 坂東鶴之助(4代目)
妹尾太左衛門 = 嵐三右衛門(10代目)
鳥見役助五郎 = 浅尾奥山(8代目)
下男与助 = 市川新之助(5代目)
百姓彌市 = 松本錦吾(2代目)
- 備考
- 錦秋を飾る唯一の東西大歌舞伎十月興行、4〜14日夜の部・15〜26日昼の部、士師清二作、浜昭二演出、大塚克三装置
- 場名など
- 新町井筒屋封印切〜新口村
- 配役
-
亀屋忠兵衛 = 片岡仁左衛門(13代目)
傾城梅川 = 嵐雛助(10代目)
親孫右衛門 = 澤村訥子(8代目)
丹波屋八右衛門 = 嵐吉三郎(7代目)
槌屋治右衛門 = 嵐三右衛門(10代目)
忠三郎の女房 = 浅尾奥山(8代目)
井筒屋おゑん = 松本錦吾(2代目)
田舎大盡 = 中村政之助(2代目)
女郎鳴渡瀬 = 松之亟1
女郎喜代川 = 嵐雛治
太鼓持喜作 = 獅道
仲居おあい = 尾上笹太郎
仲居お玉 = 雛太郎
太鼓持 = 八重十郎
太鼓持 = 良之助
太鼓持 = 当二郎
太鼓持 = い千助
仲居 = 関二郎
仲居 = 鯉子
仲居 = 片岡彦太郎
- 備考
- 錦秋を飾る唯一の東西大歌舞伎十月興行、4〜14日夜の部・15〜26日昼の部