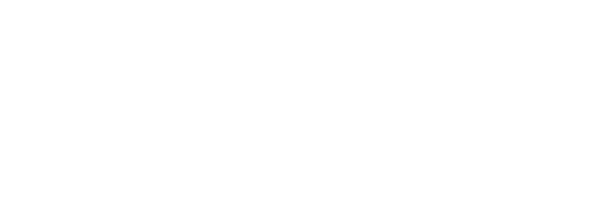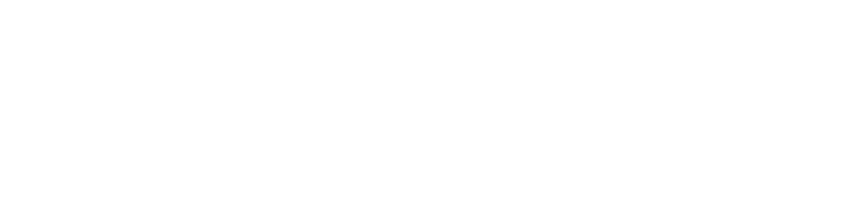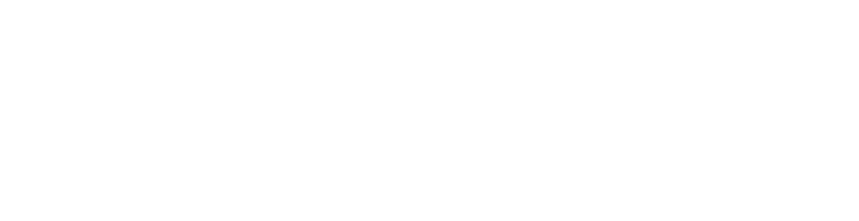南座 1946年03月
-
昼の部1の1
-
昼の部1の2
-
昼の部2
-
昼の部3
-
夜の部1
-
夜の部2
-
夜の部3
-
夜の部4
- 場名など
- 源太勘當場
- 配役
-
梶原源太景季 = 市川寿美蔵(6代目)
横須賀軍内 = 市川團次郎(2代目)
茶道珍才 = 中村梅之助
梶原平治景高 = 中村翫雀(4代目)
母延寿 = 中村霞仙(2代目)
腰元千鳥 = 中村富十郎(4代目)
- 備考
- 弥生興行 東西合同大歌舞伎、1〜13日昼の部、14〜25日夜の部
- 場名など
- 無間鐘
- 配役
-
梅ヶ枝 = 中村富十郎(4代目)
横須賀軍内 = 市川團次郎(2代目)
母延寿 = 中村霞仙(2代目)
- 備考
- 弥生興行 東西合同大歌舞伎、藤間藤三郎振付、梅屋勝之輔作詞、文楽座出演、1〜13日昼の部、14〜25日夜の部
- 場名など
- 天満紙屋治兵衛内〜曽根崎大和屋
- 配役
-
紙屋治兵衛 = 中村翫雀(4代目)
粉屋孫右衛門 = 嵐吉三郎(7代目)
舅五左衛門 = 市川九團次(3代目)
大和屋傳兵衛 = 浅尾奥山(8代目)
丁稚三五郎 = 中村扇雀(2代目)
紙屋伜勘太郎 = 林玉緒
紀の国屋のお杉 = 松鶴
紀の国屋小春 = 實川延二郎(2代目)
女房おさん = 中村富十郎(4代目)
- 備考
- 弥生興行 東西合同大歌舞伎、近松門左衛門作、食満南北脚色、玩辞樓十二曲の内、1〜13日昼の部、14〜25日夜の部
- 場名など
- 松江邸広間〜同玄関先
- 配役
-
使僧北谷道海実は河内山宗俊 = 市川寿美蔵(6代目)
家老高木小左衛門 = 嵐吉三郎(7代目)
重役北村大膳 = 市川九團次(3代目)
近習山野周助 = 嵐鯉昇(4代目)
近習間宮帯刀 = 中村紫香
近習大橋伊織 = 三津右衛門
近習黒澤要人 = 中村政之助(2代目)
腰元浪路 = 扇女改めあやめ
近習頭宮崎数馬 = 實川延二郎(2代目)
松江出雲守 = 中村翫雀(4代目)
- 備考
- 弥生興行 東西合同大歌舞伎、河竹黙阿弥作、1〜13日昼の部、14〜25日夜の部
- 場名など
- 配役
-
佐藤忠信実は源九郎狐 = 市川寿美蔵(6代目)
静御前 = 中村翫雀(4代目)
- 備考
- 弥生興行 東西合同大歌舞伎、文楽座太夫三味線特別出演、文楽座出演、1〜13日夜の部、14〜25日昼の部
- 場名など
- 何れも野島くめの家で 晴れた日に〜その夜その朝〜その家の裏で
- 配役
-
ハワイ生まれの第二世山田日出夫 = 中村翫雀(4代目)
お仙の伜大作 = 坂東鶴之助(4代目)
由やん = 市川九團次(3代目)
吉村巡査 = 浅尾奥山(8代目)
利三郎 = 三津右衛門
矢代真理 = 中村芳子
イカリ軒の後家お仙 = 英太郎(初代)
野島くめ = 中村富十郎(4代目)
- 備考
- 弥生興行 東西合同大歌舞伎、郷田悳作並演出、大塚克三装置、1〜13日夜の部、14〜25日昼の部
- 場名など
- 京都祗園茶屋花菱〜同四條河原
- 配役
-
菊地半九郎 = 市川寿美蔵(6代目)
坂田市之助 = 中村霞仙(2代目)
菊地ノ若黨八介 = 市川團次郎(2代目)
お染の父与兵衛 = 市川九團次(3代目)
坂田源三郎 = 嵐吉三郎(7代目)
仲居お雪 = 松鶴
若松の遊女お花 = 松本錦吾(2代目)
若松の遊女お染 = 中村富十郎(4代目)
- 備考
- 弥生興行 東西合同大歌舞伎、岡本綺堂作、1〜13日夜の部、14〜25日昼の部
- 場名など
- 配役
-
子守 = 中村芳子
- 備考
- 弥生興行 東西合同大歌舞伎、1〜13日夜の部、14〜25日昼の部