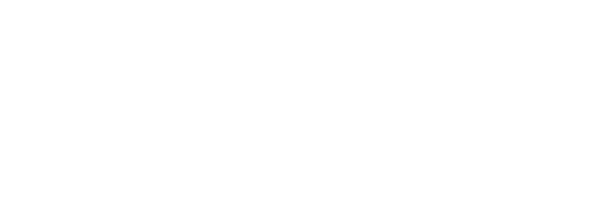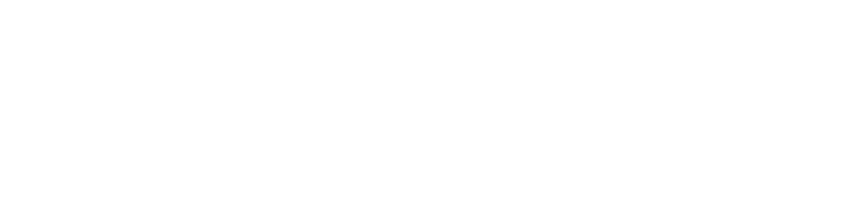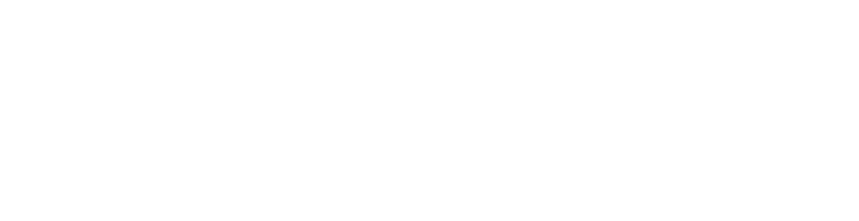御園座 1947年11月
-
昼夜入替1
-
昼夜入替2
-
昼夜入替3
-
昼夜入替1
-
昼夜入替2
-
昼夜入替3
-
昼夜入替4
- 場名など
- 角力小屋
- 配役
-
濡髪長五郎 = 市川段四郎(3代目)
茶亭 = 市川荒次郎(2代目)
弟子閂 = 市川猿三郎(初代)
三原有右衛門 = 市川左文次(2代目)
平岡郷左衛門 = 市川升太郎(2代目)
見物の若い者 = 羽之助
見物の若い者 = 久我十郎
見物の若い者 = 左市
見物の仲居 = 笹次
見物の仲居 = 笹之助
見物の仲居 = 政子
角力の見物 = 喜三太
角力の見物 = 喜三江
角力の見物 = 喜の子
吾妻 = 市川松蔦(3代目)
放駒長吉・山崎屋與五郎 = 守田勘弥(14代目)
- 備考
- 東京大歌舞伎、市川猿之助劇團公演、竹田出雲作、2〜11日昼の部、12〜21日夜の部(昼の部一幕目、夜の部三幕目)
- 場名など
- 配役
-
童子・稲荷明神 = 市川猿之助(2代目)
三條小鍛冶宗近 = 守田勘弥(14代目)
弟子冬彦 = 松本高麗五郎(初代)
弟子秋彦 = 市川笑猿(2代目)
巫女 = 市川松蔦(3代目)
勅使橘道成 = 坂東秀調(4代目)
- 備考
- 東京大歌舞伎、市川猿之助劇團公演、木村富子作、鶴澤道八作曲、杵屋佐吉作曲、花柳壽輔振付、2〜11日昼の部、12〜21日夜の部
- 場名など
- 誕生八幡宮境内笹野宅〜目黒薩州候邸内菱川宅〜行人坂上千草屋~同裏手二階座敷~行人坂上目黒〜飴屋
- 配役
-
菱川源五兵衛 = 市川猿之助(2代目)
菱川の中間事助 = 市川荒次郎(2代目)
笹野杉齋 = 團升
手代茂三郎 = 松本高麗五郎(初代)
千草屋女房おあき = 市川猿三郎(初代)
千草屋治右衛門 = 市川左文次(2代目)
富士屋の後家おきた = 坂東秀調(4代目)
百姓 = 羽之助
百姓 = 左市
小女 = 市川喜太郎
手習子 = 政子
手習子 = 喜三江
手習子 = 喜の子
千草屋娘おまん = 尾上菊次郎(4代目)
笹野三五兵衛 = 守田勘弥(14代目)
- 備考
- 東京大歌舞伎、市川猿之助劇團公演、岡鬼太郎作、2〜11日昼の部、12〜21日夜の部(昼の部三幕目、夜の部一幕目)
- 場名など
- 工藤舘對面
- 配役
-
工藤左衛門祐経 = 市川猿之助(2代目)
曽我五郎時致 = 市川段四郎(3代目)
曽我十郎祐成 = 守田勘弥(14代目)
鬼王新左衛門 = 市川荒次郎(2代目)
近江小藤太成家 = 團升
八幡三郎行氏 = 松本高麗五郎(初代)
梶原平三景時 = 市川左文次(2代目)
梶原平次景高 = 猿四郎
大名 = 羽之助
大名 = 久我十郎
大名 = 左市
大名 = 市川喜太郎
大名 = 喜三太
喜瀬川亀鶴 = 市川松蔦(3代目)
化粧坂少将 = 市川笑猿(2代目)
大磯の虎 = 澤村源之助(5代目)
舞鶴 = 尾上菊次郎(4代目)
- 備考
- 東京大歌舞伎、市川猿之助劇團公演、2〜11日夜の部、12〜21日昼の部
- 場名など
- 配役
-
夜叉王 = 市川猿之助(2代目)
姉娘桂 = 尾上菊次郎(4代目)
妹娘楓 = 澤村源之助(5代目)
楓の聟春彦 = 松本高麗五郎(初代)
下田五郎景安 = 市川笑猿(2代目)
金窪兵衛行親 = 市川九團次(3代目)
金窪の家来 = 市川升太郎(2代目)
金窪の家来 = 猿四郎
金窪の家来 = 羽之助
金窪の家来 = 左市
修禅寺の僧 = 團升
源左金吾頼家 = 守田勘弥(14代目)
- 備考
- 東京大歌舞伎、市川猿之助劇團公演、岡本綺堂作、2〜11日夜の部、12〜21日昼の部
- 場名など
- 配役
-
狐忠信 = 市川猿之助(2代目)
藤太 = 市川段四郎(3代目)
軍兵 = 市川左文次(2代目)
軍兵 = 市川升太郎(2代目)
軍兵 = 猿四郎
軍兵 = 羽之助
軍兵 = 久我十郎
軍兵 = 左市
軍兵 = 市川喜太郎
軍兵 = 喜三太
小狐 = 市川笑猿(2代目)
静御前 = 尾上菊次郎(4代目)
- 備考
- 東京大歌舞伎、市川猿之助劇團公演、2〜11日夜の部、12〜21日昼の部
- 場名など
- 源氏店
- 配役
-
蝙蝠安 = 市川段四郎(3代目)
和泉屋多左衛門 = 團升
およし = 市川猿三郎(初代)
藤八 = 市川左文次(2代目)
お富 = 尾上菊次郎(4代目)
與三郎 = 守田勘弥(14代目)
- 備考
- 東京大歌舞伎、市川猿之助劇團公演、三世瀬川如皐作、2〜11日夜の部、12〜21日昼の部