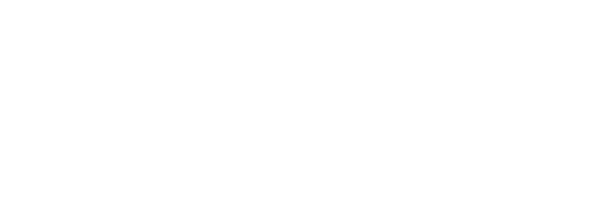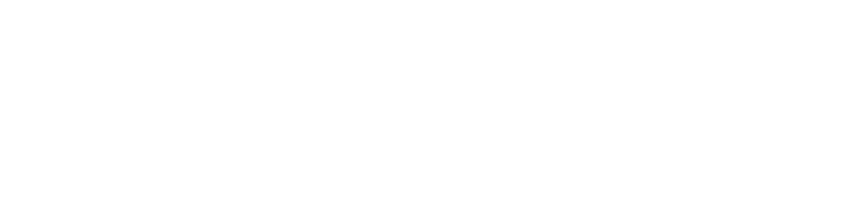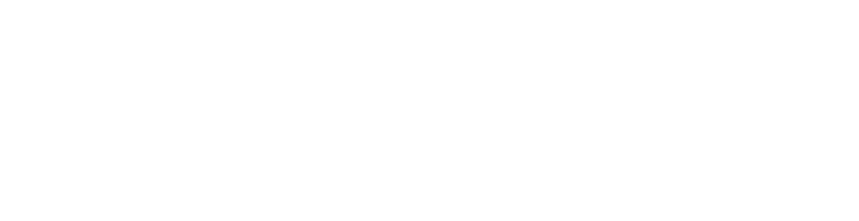歌舞伎座 1969年12月
-
昼の部1
-
昼の部2
-
昼の部3
-
夜の部1
-
夜の部2
-
夜の部3
- 場名など
- その日の雪、大野屋離れ座敷〜同茶庭〜大野屋の母屋美津の部屋〜同茶庭〜大野屋離れ座敷
- 配役
-
両替屋丁稚実は矢頭右衛門七 = 市川男女蔵(5代目)
内蔵之助の嫡子大石主税 = 坂東薪水(8代目)
元国家老大石内蔵之助 = 坂東好太郎(初代)
呉服商大野屋の娘美津 = 長谷川澄子
乳母くめ = 澤村源之助(5代目)
- 備考
- 吉例第三回大川橋蔵特別公演、成沢昌茂作・演出
- 場名など
- 道行より押戻しまで
- 配役
-
白拍子花子 = 大川橋蔵(2代目)
大館左馬五郎照剛 = 市村羽左衛門(17代目)
所化西念坊 = 市川銀之助(初代)
所化東仙坊 = 市村竹松(5代目)
所化雲念坊 = 坂東亀之助
所化久念坊 = 澤村六郎(2代目)
所化悟念坊 = 澤村由次郎(5代目)
所化喜観坊 = 坂東勲
所化辛張坊 = 峰蘭太郎
所化陸釈坊 = 市川滝之丞(3代目)
所化阿歓坊 = 坂東橘(初代)
所化不動坊 = 中村千弥(2代目)
所化阿面坊 = 坂東かしく
所化要心坊 = 中村時寿(初代)
所化咲蘭坊 = 片岡松燕(2代目)
所化普門坊 = 澤村小主水(4代目)
所化治南坊 = 坂東吉二郎
所化覚連坊 = 中村好雄
鱗四天 = はじめ
鱗四天 = 市川容之助
鱗四天 = 市川芳次郎
鱗四天 = 坂東羽之助
鱗四天 = 中村時三郎(初代)
鱗四天 = 片岡市松
鱗四天 = 岩井大三郎
鱗四天 = 片岡松三郎
鱗四天 = 市川八百恵
鱗四天 = 中村吉之助(2代目)
鱗四天 = 由蔵
鱗四天 = 坂東大六
- 備考
- 吉例第三回大川橋蔵特別公演、松島庄三郎・松島寿三郎・田中佐十次郎出演、藤間勘十郎振付
- 場名など
- 桜伝内、亘理城本丸書院〜江戸都座の楽屋〜箱崎河岸〜青葉城本丸庭先〜一風斎の道場〜仙姫の居室〜城中の石牢〜奥州屋の表と座敷〜陸前街道〜都座の舞台
- 配役
-
桜伝内・石母田進之丞 = 大川橋蔵(2代目)
仙姫 = 藤間紫
市川団十郎 = 市村羽左衛門(17代目)
伊達藩城代家老亘理城主伊達安房 = 坂東好太郎(初代)
医者島田玄庵 = 澤村宗之助(2代目)
安房の家臣石塚富八郎 = 片岡孝夫
剣術指南役長沼一風斎 = 大山克巳
安房の御側用人石母田左太夫 = 市川八百蔵(9代目)
伊達藩主伊達綱村 = 市川男女蔵(5代目)
伊達藩国家老三沢信濃 = 片岡市蔵(5代目)
石塚兄弟の妹お藤 = 波野久里子
師匠都兵五郎 = 尾上鯉三郎(3代目)
弟石川万之助 = 市川銀之助(初代)
伊達藩審判役近江老人 = 助高屋小伝次(2代目)
伊達安房の重臣黒川大学 = 中川秀夫
弟子伝太郎・中間姿の伝太郎 = 林家珍平
信濃の家来後藤十郎太 = 楠本健二
安房の家臣森新十郎 = 坂東勲
安房の家臣河内靱負 = 坂東市之丞
三輪田五太夫 = 坂東薪蔵(3代目)
山中三郎太 = 澤村六郎(2代目)
粂村芳十郎 = 澤村由次郎(5代目)
番頭源七 = 尾上新七(5代目)
巡礼の老爺 = 坂東市太郎(2代目)
綱村の正室北の方 = 市川福之助(3代目)
仙姫の侍女おきぬ = 桃山みつる
女形都あやめ = 中村千弥(2代目)
町娘お里 = 坂東橘(初代)
内儀お粂 = 片岡松燕(2代目)
町娘お光 = 坂東かしく
贔屓の女おりき = 澤村小主水(4代目)
老女 = 坂東羽三郎(初代)
伊達安房の重臣鈴木作兵衛 = 坂東春之助
伊達安房の重臣酒井兵庫 = 尾上鯉之助
団十郎の弟子団吉 = 市川芳次郎
弟子伝三・中間姿の伝三 = 池信一
木戸番の留吉 = 神戸瓢介
介添役の伊達藩士石川善次郎・供侍 = 片岡市松
女中おしま = 伊藤みどり
都座の楽屋番・供侍 = 市川滝三郎(2代目)
都座の頭取・供侍 = 中村時三郎(初代)
都座の男衆 = 市川容之助
都座の男衆 = 由蔵
駕舁・仙姫の駕舁 = 坂東羽之助
駕舁・仙姫の駕舁 = はじめ
黒装束の刺客・信濃の刺客・都座一座の役者 = 泉
黒装束の刺客・信濃の刺客・都座一座の役者 = 平河
黒装束の刺客・信濃の刺客・都座一座の役者 = 藤原
黒装束の刺客・信濃の刺客・都座一座の役者 = 加藤
黒装束の刺客・信濃の刺客 = 高杉
黒装束の刺客・供侍・信濃の刺客・都座一座の役者 = 名護屋
侍・供侍・信濃の刺客 = 川浪
侍・供侍・信濃の刺客 = 芹川
侍・供侍 = 岡田
侍・供侍 = 北川
侍 = 沢村
侍・供侍 = 芳村
侍・信濃の刺客 = 仲塚
亘理城の牢番 = 坂東大六
仙姫の駕舁 = 片岡松三郎
仙姫の駕舁 = 岩井大三郎
供侍 = 堀
供侍 = 鶴田
信濃の刺客 = 内藤
信濃の刺客 = 小沢
侍女 = 若菜千満
侍女 = 幸
侍女 = 佐野布美子
侍女 = 伊藤
侍女 = 左男女
都座一座の役者 = 坂東鶴枝(初代)
都座一座の役者 = 市川八百恵
都座一座の役者 = 孝三郎
通行人 = 多ぜい
息子伝之介 = 大川辰五郎
小姓 = 勘吉
巡礼の女の子 = 坂東うさぎ
- 備考
- 吉例第三回大川橋蔵特別公演、大川辰五郎初舞台、川口松太郎作、田中喜三脚色、巌谷槇一・田中喜三演出
- 場名など
- 不忍池近くの岡場所「よね屋」〜同−松の内の夕刻−〜同お新の部屋−二月初旬〜同女たちの溜り部屋〜日光門跡下屋敷横大根畑〜もとの「よね屋」〜同−三月初旬〜同お新の部屋〜「よね屋」−四月初旬
- 配役
-
若い女お新 = 波野久里子
江口房之助 = 片岡孝夫
年増女菊次 = 藤間紫
行徳の梅 = 中川秀夫
女主人おみの = 一条久枝
お新の客 = 坂東市之丞
店の女みどり = 瀬戸よう子
店の女おせき = 桃山みつる
店の女吉野 = 常磐みどり
客 = 岩井大三郎
客 = 片岡松三郎
客 = 坂東吉二郎
客 = 吉之助
老人の客 = 市川芳次郎
夜鷹蕎麦屋 = 片岡市之助
酔っぱらいの男 = 芳村浩明
酔っぱらいの男 = 片岡市松
行徳の梅の乾分 = 仲塚
行徳の梅の乾分 = 芹川
行徳の梅の乾分 = 北川
行徳の梅の乾分 = 小沢
行徳の梅の乾分 = 内藤
前の店の女 = 伊藤みどり
- 備考
- 吉例第三回大川橋蔵特別公演、山本周五郎原作、中村登脚本・演出
- 場名など
- 配役
-
傾城薄雲太夫のちに蜘蛛の精・座頭歌市 = 大川橋蔵(2代目)
源頼光 = 市村羽左衛門(17代目)
坂田金時 = 市川男女蔵(5代目)
碓氷貞光 = 坂東薪水(8代目)
女童加賀美 = 大川辰五郎
- 備考
- 吉例第三回大川橋蔵特別公演、大川辰五郎初舞台、松島庄三郎・杵屋五三助・常磐津三東勢太夫・常磐津松寿・田中佐十次郎出演、藤間勘十郎振付
- 場名など
- 湯治場の休日、箱根の湯宿桔梗屋の玄関口〜宿の二階〜階下の治兵衛の居間〜離れの菊の間〜もとの居間〜山の麓の水車小屋〜もとの宿の居間〜座敷の横手〜桔梗屋近くの三枚橋
- 配役
-
銭形平次・若い按摩徳の市 = 大川橋蔵(2代目)
宿の亭主治兵衛 = 坂東好太郎(初代)
宿の女房おかじ = 藤間紫
旅廻りの呉服屋新助 = 片岡孝夫
材木問屋の娘おせつ = 波野久里子
石見守の孫娘おしの = 葉山葉子
女房お静 = 長谷川季子
代官手附篠田権四郎 = 市川八百蔵(9代目)
下僕小堀庄左衛門 = 澤村宗之助(2代目)
乾分八五郎 = 林家珍平
易者福原玄斎 = 大山克巳
手代与之吉 = 坂東吉弥(2代目)
目明し早川の紋次 = 中川秀夫
住職竜哲和尚 = 利根川金十郎(初代)
水車小屋の番人伊平 = 尾上鯉之助
板前の喜七 = 坂東春之助
下ッ引亀吉 = 神戸瓢介
宿の番頭忠助 = 池信一
宿の女中およね = 桃山みつる
宿の女中おまつ = 幸京子
宿の女中おうめ = 佐野布美子
茶店の老婆 = 市川福之助(3代目)
講中の男・講中の男浪人 = 川浪
講中の男・講中の男浪人 = 名護屋
講中の男・講中の男浪人 = 泉
講中の男浪人 = 楠本
講中の男無頼漢 = 平河
講中の男無頼漢 = 藤原
講中の男無頼漢 = 加藤
講中の男無頼漢 = 峰
講中の男無頼漢 = 仲塚
講中の男無頼漢 = 岡田
講中の男無頼漢 = 高杉
- 備考
- 吉例第三回大川橋蔵特別公演、野村胡堂原作、矢田弥八脚本・演出