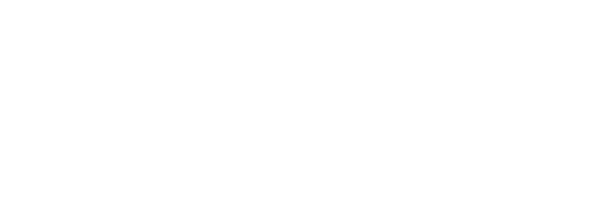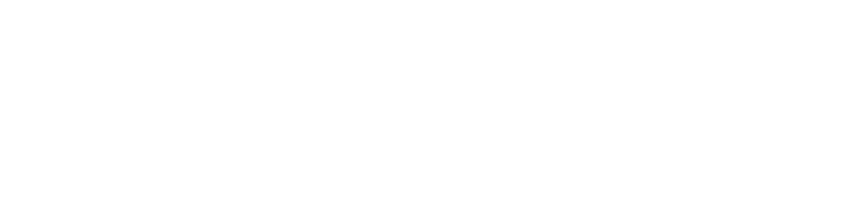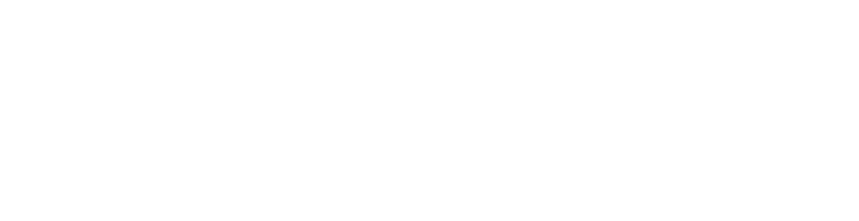国立劇場(大劇場) 1972年12月
-
一回公演1
-
一回公演2
-
一回公演3
- 場名など
- 植木屋、浅草観音〜染井植木屋〜染井植木屋奥庭菊畑
- 配役
-
腰元おたか・お蘭の方実はおたか = 中村雀右衛門(4代目)
小春屋弥七実は千崎弥五郎 = 中村扇雀(2代目)
植木屋杢右衛門実は竹森喜太八 = 河原崎権十郎(3代目)
からくり屋太四郎実は近藤源四郎 = 中村松若(初代)
杢右衛門妹お市 = 市川門之助(7代目)
太四郎妹お新 = 大谷友右衛門(8代目)
高家の家来種森兵内 = 岩井半四郎(10代目)
植木屋の下職源市 = 澤村六郎(2代目)
植木屋の下職平六 = 市川福太郎
上燗屋喜三郎 = 中村京右衛門(初代)
からくり屋九郎八実は大須賀団八 = 市川段猿(2代目)
植木屋の下職藤松 = 山崎権一(初代)
高家の供侍石坂金吾 = 市川喜猿(4代目)
老女門田 = 市川福之助(3代目)
腰元葉末 = 中村小山三(2代目)
腰元紅葉 = 中村京葭(初代)
腰元白菊 = 澤村小主水(4代目)
腰元露芝 = 澤村可川(初代)
腰元萩乃 = 片岡松燕(2代目)
腰元桔梗 = 中村千弥(2代目)
腰元松ヶ枝 = 市川升寿(初代)
腰元初島 = 市川鯉紅(初代)
仲間可助・駕籠の中間 = 中村扇二郎
参詣人の男・高家の供侍 = 仲三
参詣人の男・高家の供侍 = 喜蔵
参詣人の男・高家の供侍 = 喜二郎
参詣人の男・中間 = 段二
参詣人の男・中間 = 中村富三郎
参詣人の男・高家の供侍 = 市川升一郎
参詣人の男・中間 = 山崎咲輔(2代目)
参詣人の男・中間 = 咲三郎
参詣人の男・高家の供侍 = 米太郎
参詣人の男・駕籠の中間 = 岩井若次郎
参詣人の男・駕籠の中間 = 昭之助
参詣人の男・高家の供侍 = 澤村大蔵(初代)
高家の供侍 = 鶴田耕裕
中間 = 市川升助(初代)
駕籠の中間 = 咲二郎
参詣人の女・腰元 = 澤村国三郎
参詣人の女・腰元 = 喜三太
参詣人の女・腰元 = 澤村国世
参詣人の子供 = 勘吉
- 備考
- 第五十四回(大劇場)、土曜日のみ一日二回公演、
- 場名など
- 南部坂雪の別れ、芸州侯下屋敷葉泉院御殿〜芸州侯下屋敷葉泉院居間〜芸州侯下屋敷外
- 配役
-
大星由良之助良金 = 市川猿之助(3代目)
後室葉泉院 = 澤村訥升(5代目)
戸田の局 = 澤村田之助(6代目)
侍女おうめ = 市村家橘(17代目)
渋川五太夫 = 市川猿三郎(初代)
取つぎの侍 = 市川猿十郎(3代目)
腰元あかね = 市川升寿(初代)
腰元置霜 = 市川松尾(3代目)
腰元みゆき = 市川升之丞(2代目)
腰元夜雨 = 澤村可川(初代)
腰元麻月 = 片岡松燕(2代目)
腰元笹波 = 市川鯉紅(初代)
- 備考
- 第五十四回(大劇場)、土曜日のみ一日二回公演、河竹黙阿弥作
- 場名など
- (通し)両国橋橋詰〜松浦邸書院〜松浦邸玄関先
- 配役
-
松浦鎮信 = 中村勘三郎(17代目)
大高源吾 = 市川海老蔵(10代目)
宝井其角 = 河原崎権十郎(3代目)
源吾妹お縫 = 澤村精四郎
鵜飼左司馬 = 市川子團次(2代目)
淵部市右衛門 = 市川段四郎(4代目)
里見幾之丞 = 中村米吉(4代目)
早瀬近吾 = 市村家橘(17代目)
江川文太夫 = 中村勘五郎(13代目)
中間梅助 = 中村清五郎(3代目)
中間松蔵 = 中村山左衛門(5代目)
門番平内 = 中村京右衛門(初代)
馬の口取 = 鶴田耕裕
足軽 = 喜二郎
足軽 = 中村扇二郎
足軽 = 中村扇蔵
足軽 = 昭之助
足軽 = 山崎咲輔(2代目)
足軽 = 咲二郎
- 備考
- 第五十四回(大劇場)、土曜日のみ一日二回公演、勝諺蔵作、通し狂言