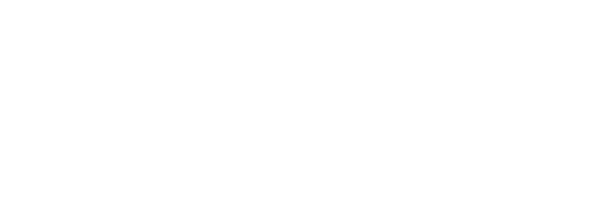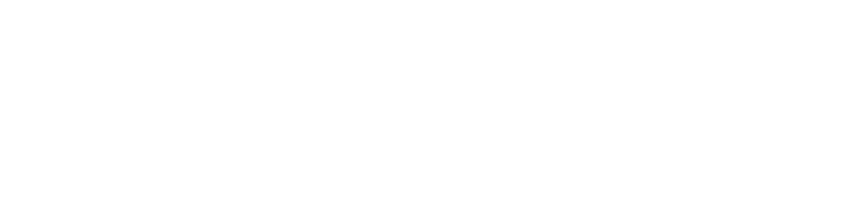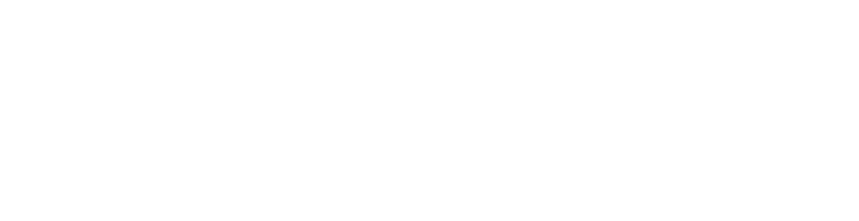歌舞伎座 1960年02月
-
昼の部1
-
昼の部2
-
昼の部3
-
夜の部1
-
夜の部2
-
夜の部3
- 場名など
- 印旛沼渡し小屋〜宗吾住居子別れ〜東叡山直訴
- 配役
-
木内宗吾 = 松本幸四郎(8代目)
渡し守甚兵衛・松平伊豆守 = 市川中車(8代目)
幻長吉・将軍徳川家綱 = 守田勘弥(14代目)
宗吾女房おさん = 中村又五郎(2代目)
久世大和守 = 市村家橘(16代目)
井上河内守 = 市川九蔵(5代目)
酒井若狭守 = 市川高麗蔵(10代目)
寛永寺座主知照 = 中村種五郎(2代目)
三浦志摩守 = 中村吉十郎(2代目)
青山伯耆守 = 市川猿三郎(初代)
見廻りの役人・稲葉丹波守 = 松本高麗五郎(2代目)
松平右京太夫 = 澤村宗五郎(2代目)
伊丹肥前守 = 市川升太郎(2代目)
秋元但馬守 = 市川春猿(初代)
市橋下総守 = 加賀屋歌蔵(初代)
旗本近藤舎人 = 中村吉五郎(初代)
旗本水野五郎兵衛 = 松本幸之助
旗本飯塚兵馬 = 松本錦弥
旗本本田主膳 = 市川五百蔵(2代目)
村の女房おくわ・榊原式部少輔 = 片岡愛之助(5代目)
村の女房おまき・浅野摂津守 = 中村万之丞
村の女房おきよ = 中村吉之助(2代目)
村の女房おたね = 松本幸雀(初代)
中間・番士 = 市川中之助(3代目)
侍僧 = 又之助
小姓 = いてふ
番太・お側衆 = 中村駒七
番太 = 政次郎
番太・お側衆 = 羽寿蔵
番太 = 撫子
お側衆 = 政次郎
お側衆 = 市川左喜松(3代目)
お側衆 = 坂東慶昇
お側衆 = 中村又雄
番士 = 錦之丞
番士 = 市川容之助
番士 = 中村仲三郎
伜彦七 = 坂東喜の字
次男徳松 = 茂信
娘おとう = 充美
- 備考
- 初日特定狂言1
- 場名など
- 配役
-
息女朝子 = 中村歌右衛門(6代目)
僧パアデレ・秋月ジョアンの幻影 = 實川延二郎(2代目)
侍 = 市川九蔵(5代目)
若侍 = 中村藤太郎
ポルトガル人 = 中村万之丞
唐人 = 加賀屋歌蔵(初代)
司祭 = 松本錦弥
助祭 = 市川五百蔵(2代目)
聖歌隊 = いてふ
女 = 中村小山三(2代目)
女 = 加賀屋歌江(2代目)
女 = 市川春猿(初代)
女の童 = 中村吉之助(2代目)
聖歌隊 = 渡辺由紀子
聖歌隊 = 長島ひろ子
聖歌隊 = 高木真弓
聖歌隊 = 福田則子
聖歌隊 = 北見とも子
聖歌隊 = 持田聿子
聖歌隊 = 小高良子
聖歌隊 = 村治笙子
聖歌隊 = 渡辺国夫
聖歌隊 = 高宝財
聖歌隊 = 進藤三則
聖歌隊 = 本橋敏和
聖歌隊 = 和泉寿時
聖歌隊 = 熊谷和夫
- 備考
- 初日特定狂言2、石田潭月作詞、平井澄子作曲、山口蓬春美術
- 場名など
- 寺子屋
- 配役
-
舎人松王丸 = 中村勘三郎(17代目)
武部源蔵 = 市川猿之助(2代目)
松王女房千代 = 中村歌右衛門(6代目)
源蔵女房戸浪 = 澤村宗十郎(8代目)
春藤玄蕃 = 市川中車(8代目)
涎くり与太郎 = 市村家橘(16代目)
御台所園生の前 = 中村芝雀(6代目)
百姓 = 中村吉十郎(2代目)
百姓 = 片岡愛之助(5代目)
百姓 = 中村種五郎(2代目)
百姓 = 松本高麗五郎(2代目)
百姓 = 澤村宗五郎(2代目)
百姓 = 加賀屋歌蔵(初代)
百姓 = 實川延正
百姓 = 片岡我勇(2代目)
捕手 = 市川芳次郎
捕手 = 中村仲助
捕手・陸尺 = 中村杵蔵
捕手 = 市川中之助(3代目)
捕手 = 中村時三郎(初代)
捕手 = 中村又雄
捕手 = 市川荒右衛門(2代目)
捕手 = 段次
捕手 = 市川喜三郎
捕手 = 田紀夫
陸尺 = 新八
菅秀才 = 坂東喜の字
一子小太郎 = 中村米吉(4代目)
手習子 = 伊藤茂信
手習子 = 高宝財
手習子 = 渡辺国夫
手習子 = 進藤三則
手習子 = 本橋敏和
手習子 = 和泉寿時
手習子 = 熊谷和夫
- 備考
- 初日特定狂言3
- 場名など
- 〔合邦庵室〕
- 配役
-
合邦道心 = 市川猿之助(2代目)
高安後妻玉手御前 = 中村歌右衛門(6代目)
高安俊徳丸 = 實川延二郎(2代目)
奴入平 = 市川段四郎(3代目)
息女浅香姫 = 中村芝雀(6代目)
おとく = 市川團之助(6代目)
壺井平馬 = 中村吉十郎(2代目)
講中 = 市川中蔵(2代目)
講中 = 松本幸之助
講中 = 片岡我勇(2代目)
講中 = 片岡松燕(2代目)
講中 = 市川喜猿(4代目)
講中 = 實川延寿(初代)
- 備考
- 場名など
- 配役
-
西郷吉之助 = 松本幸四郎(8代目)
山岡鉄太郎 = 市川猿之助(2代目)
中村半次郎後に桐野利秋 = 市川段四郎(3代目)
益満休之助 = 市川中車(8代目)
参謀林玖次郎 = 市川高麗蔵(10代目)
参謀付監察村田新八 = 市川染五郎(6代目)
葦田軍助 = 中村萬之助
藩主稲田求馬 = 片岡愛之助(5代目)
藩主筧孫太郎 = 中村種五郎(2代目)
覚王院義観 = 中村吉十郎(2代目)
竜王院堯忍 = 市川團之助(6代目)
旗本藤山懸三十郎 = 澤村宗五郎(2代目)
旗本田辺忠之進 = 松本幸之助
津田玄蕃の用人某 = 市川中蔵(2代目)
詰所出仕樋口某 = 市川猿三郎(初代)
詰所出仕谷村某 = 市川升太郎(2代目)
詰所出仕安場某 = 松本高麗五郎(2代目)
諸藩隊長 = 中村吉五郎(初代)
諸藩隊長 = 喜三太
諸藩隊長 = 市川五百蔵(2代目)
少年の給仕 = 市川荒次郎(3代目)
少年の給仕 = 中村仲之助
下役の僧 = 中村杵蔵
下役の僧 = 中村時三郎(初代)
書役 = 我久三郎
書役 = 市川左喜松(3代目)
少年の給仕 = 坂東守弥
- 備考
- 初日特定狂言4、真山青果作、巌谷槇一演出
- 場名など
- 熊谷宿の土手〜魚売り七兵衛住居〜同(十年後)〜浜町川岸〜鈴ヶ森題目塚の前〜岩井家の居間(宵)〜同(朝)〜鳥羽屋の茶の間〜横山町検校の寝間〜鳥羽屋の居間〜不知火検校の居間〜同〜同〜横山町の往来
- 配役
-
魚売り七兵衛・七之助の杉の市・不知火検校 = 中村勘三郎(17代目)
生首の倉吉後に手引きの幸吉 = 守田勘弥(14代目)
鳥羽屋丹治 = 市川中車(8代目)
鳥羽屋玉太郎 = 實川延二郎(2代目)
岩井藤十郎 = 澤村宗十郎(8代目)
七兵衛女房おしん = 市川松蔦(3代目)
奥方浪江 = 片岡我童(13代目)
湯島のおはん = 中村芝雀(6代目)
初代検校 = 市川團蔵(8代目)
母おもと = 尾上多賀之丞(3代目)
夜鷹宿のおつま = 中村芝鶴(2代目)
若旦那長次郎 = 市村家橘(16代目)
指物師房五郎 = 中村又五郎(2代目)
正の市 = 市川染五郎(6代目)
妻おらん = 市川團之助(6代目)
因果物師勘次 = 中村吉十郎(2代目)
手引きの角蔵 = 片岡愛之助(5代目)
同心石塚喜内 = 松本高麗五郎(2代目)
町人芳造 = 市川升太郎(2代目)
町人正吉 = 加賀屋歌蔵(初代)
町人春蔵 = 中村吉五郎(初代)
町人助七 = 市川中蔵(2代目)
長屋の男 = 澤村宗五郎(2代目)
若い者 = 市川五百蔵(2代目)
長屋女房おりく = 加賀屋鶴助(初代)
町娘おくみ = 中村小山三(2代目)
小間使 = 中村時蝶(初代)
小間使 = 中村千弥(2代目)
町の女房 = 中村吉弥(2代目)
町の娘 = 坂東かしく
大工 = 羽寿蔵
猿廻し = 坂東慶昇
弟子 = 中村仲太郎
弟子 = 中村時三郎(初代)
弟子 = 訥尾平
弟子 = 市川容次郎
弟子 = 中丸
弟子 = 鶴八郎
陸尺 = 新八
陸尺 = 中村杵蔵
手先 = 中村仲三郎
手先 = 中村仲助
手先 = 撫子
手先 = 芝三
手先 = 中村又雄
手先 = 田紀夫
手先 = 市川荒右衛門(2代目)
手先 = 市川芳次郎
女中 = 仲次
女中 = 市川中弥
群衆 = 大ぜい
供の者 = 大ぜい
祭の見物人 = 大ぜい
伜七之助 = 武知稚文
- 備考
- 初日特定狂言5、宇野信夫作並演出